MEMBER
当社は地質調査、物理探査、土木設計の領域で多様なプロジェクトに携わっており、専門的なスキルを備えた社員が活躍しています。今回のクロストークでご紹介するのは土木設計のプロジェクト。急傾斜地の下に建つ家屋とそこで暮らす人たちを斜面崩壊から守ることがミッション。その取り組みについて、上司でありチームをまとめる主担当者と、若手設計担当者に話してもらいました。
-

設計技術部
道路砂防グループT. S.
1992年入社/土木工学科出身
-

設計技術部
道路砂防グループT. M.
2021年入社/理工学部出身
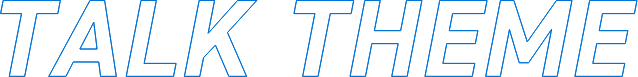 [土木設計プロジェクト]
[土木設計プロジェクト]
急傾斜地の下に建つ家屋と、
そこで暮らす人たちを斜面倒壊から守る

TALK 01
斜面崩壊のリスクに加え
工事を阻む立地が課題に

- まず、最初にプロジェクトの概要を話さないと、このクロストークを見てくれた学生のみなさんはイメージしにくいよね。今回紹介するプロジェクトは、急傾斜地の下に10軒以上の家屋が建っていて、土砂や落石などの斜面崩壊による被害を防ぐために、どんな対策工法が最適なのかを選定し、工事を行うために必要な設計と仮設計画の立案を行うという内容です。

- 主な流れを説明すると、案件を落札後、設計書や特記仕様書から業務の目的を把握するとともに業務計画書を作成してお客様(ここでの発注者は自治体)の了承を得た上で業務に取り組みます。具体的には現地踏査で得た情報などをもとに概略設計を行い、必要な箇所にて土質調査を実施して予備設計により最終的な工法を選定します。そして、承諾を得られると工事を行うための詳細設計を行います。ここまでが私たちが担う役割です。

- こうした業務では、お客様(ここでの発注者は自治体)や工事を行う業者様など、さまざまな人と連携して進めていきます。当社が受けもつ工程に関しては、私が窓口としてお客様との調整やチームの進捗管理を行う主担当者を務め、T. M.君が崩壊防止施設の設計を担当しています。

- 終了した案件なら余裕をもって振り返ることができるのですが、今も取り組んでいる最中なので、少し緊張しながら話しています(笑)。私の具体的な業務としては、現地踏査や工法の選定、安定計算や構造計算、図面数量の作成、協議資料や報告書作成などが挙げられます。

- 最初の段階で現地踏査をしたわけだけれど、「なかなか難易度が高い」というのが第一印象でした。急傾斜地を200mほど上がったところに、岩が剥き出しになっていたり、浮石や転石になっている落石源があり、落石するリスクがあった。しかも、家屋が斜面に張りついていて、一般道路から工事を行う場所へアクセスするスペースがなく、重機を搬入するのがむずかしい状態でした。そのため仮設道路をつくる必要があり、それによって工法やコスト、工期も変わってくるんです。

- 正直なところ、はじめて現場を見た時は頭を抱えたくなりました(笑)。でも、条件整理をしていくうちに何となく工法や構造が頭に浮かんできて、「やってやるぞ」という気持ちになってきました。

- 頼もしい部下がいてくれて心強いです(笑)。

TALK 02
調査結果を検証して
柔軟に対応することが重要

- 今回のような落石防止も必要な工事では、基礎地盤の締まり具合が重要な要素となり、やわらかい場合は特に注意が必要なんです。土質調査を行ったところ、まさにそれに当てはまることが明らかになりました。専門用語でN値といって、ボーリング調査における標準貫入試験(63.5kgのおもりを76cmの高さから落として、地面の30cm下に沈むまでの回数を図る試験)で得られるのですが、そのN値が低かった。

- しかも、大昔の大規模崩壊で堆積した斜面でやわらかい中に岩塊が混在している複雑な状態。土質がやわらかくなっているのは、落石源の近くに水が出ていることが大きな原因だったため、排水用の水路を設ける必要があり、それも工法を選定するポイントのひとつになりました。このように業務計画段階ではわからなかったことが、現場の調査を進めていくうちに明らかになることは、決して珍しくありません。その場合、新たな調査項目を増やすことが考えられますが、工期やコストにも関係するので、お客様としっかり確認をとって対応することが重要なんです。

- それはとても大事。ある程度進めてからNGが出てしまっては、ロスが大き過ぎますから。そういうことが起きないように、常に関係者と確認をとり合うようにしています。手前味噌ですが、当社はそうした姿勢が徹底されているので、大きな手戻りはないと自信をもっています。同時に、それが慢心にならないように気をつけています。

- チーム内でもしっかりとコミュニケーションをとるようにしていて、よくT. S.さんや先輩方に相談してアドバイスをいただいています。

- 経験上、どんなところでミスをしたり、行き詰まったりしやすいのかある程度わかるので、そこを重点的にフォローするようにしています。といっても、すべてを教えるわけではありません。それでは進歩しませんから。

- 業務を進める過程で課題に突き当たったことがあるのですが、自分の知識が足りないせいなのか、方向性が間違っているからなのかがわからず迷路に入り込んでいた時に、「原点に戻って原因が何なのか分析してはどうか」とアドバイスしてくださり、それが解決のヒントになりました。それからは課題がでた際、「こんな情報があれば解決できるのでは」という予測を立てるようになりました。この予測に対して再度現地確認を実施したり、斜面安定計算や構造計算を通して、予測の裏付けを行います。

TALK 03
採用する工法が決まり
プロジェクトは次のフェーズへ

- 現場の状況やさまざまな条件を照らし合わせて検討した結果、今回のプロジェクトでは、ワイヤーロープで浮石や転石を覆って落石を防ぐ落石予防工と、崩壊土砂を受け止める待受型防護柵を組み合わせることに決定しました。そして現在は、工事に向けて詳細設計に取り掛かっているところです。ひとまず大きな山を乗り越え、またこれから大きな山を登りはじめているところでしょうか(笑)。

- まだプロジェクトの途中ですが、多くのことを学ぶことができていると感じています。現地踏査を例に挙げると、以前は先輩方に言われた箇所を写真撮影するだけでしたが、今は事前に図面を見て対策工の計画位置を想定したり、支障物などの注意点をピックアップしたり、自分で考えて撮影に臨むようになってきました。

- 確かに、近くで見ていてそれは感じるよ。そうしたことができるようになるには、たくさん経験を積む必要がある。どんなに資料を読んだり、こちらが説明しても、自分自身で経験しないと身につかない。そういう意味で、当社は若手社員がいろいろな経験を積み、成長できる会社だと思います。

- それは実感しています。今後の目標は、まず今のプロジェクトを無事完了させるために、チームに貢献すること。そして、T. S.さんをはじめ先輩方から業務の進め方を吸収して、一人立ちすることです。また、私が所属する部署ではドローン空撮など3次元データの活用に力を入れているので、そうした技術を習得したいと考えています。

- そうだね、これからはお客様へのプレゼンや設計の説明など、前面に立って活躍していくことを期待しています。T. M.君にはその能力が十分あるので、楽しみにしています。

- ありがとうございます。会社のためにも、自分自身のためにも頑張ります!
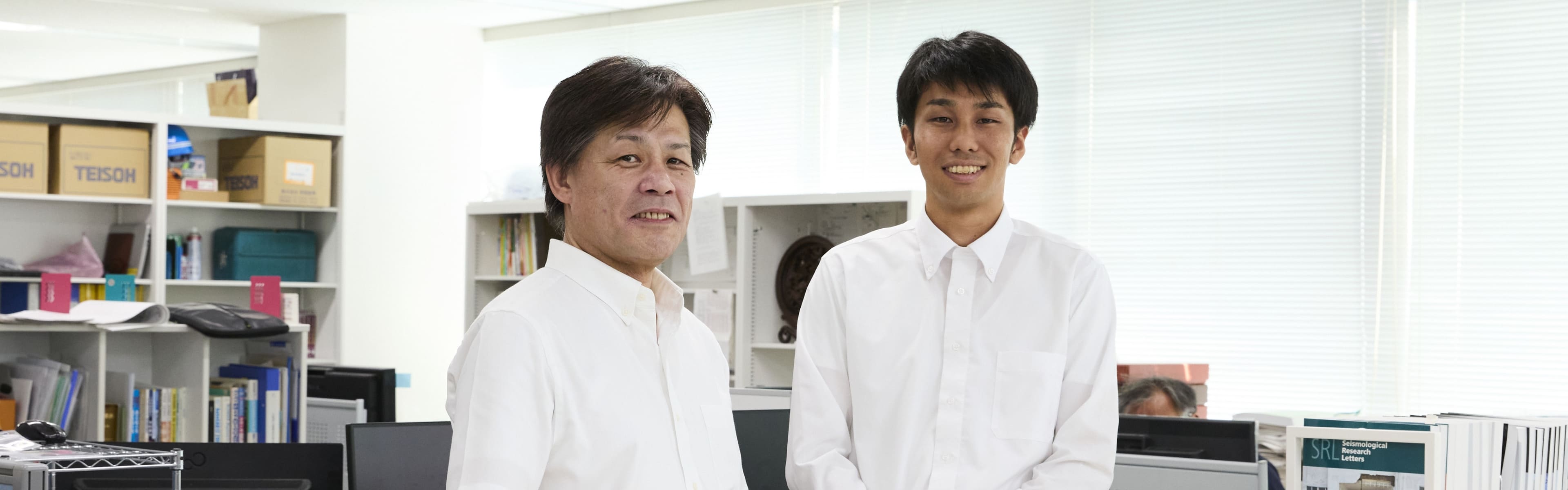
 RECRUITING SITE
RECRUITING SITE